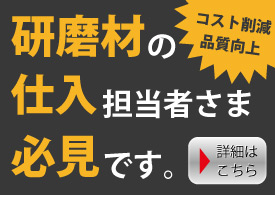研磨材の知識
研磨材の用語や知識をご紹介しています
研磨とは
研磨とは、凹凸のある個体の表面を、その個体より高度の高い物体をこすりつけることで平面を維持したり、凹凸を滑らかにしたりする事です。
身近なところではキッチンのシンクをクレンザーで磨くのも研磨ですし、木工の切断面をヤスリで滑らかにすることも研磨ということになります。
削る力が大きいと「研削」という言い方をする場合もあります。
例えば爪やすりで爪の形状を整えるのは「研削」に近いイメージで、爪の表面をつやつやに磨く事は「研磨」のイメージとなります。
あまり、はっきりとした定義はありませんが、その業界や分野、あるいは会社ごとに定義を決めているというのがほとんどです。
基本的な研磨の方法
砥石や研磨布紙などには研磨材が使用されています。
研磨材の最小構成物は「砥粒」と呼ばれ、構成する砥粒の大きさによって研磨や研削の力の大小が決まります。
例えば木工作業で考えると、木工の切断面を最初は粗めのヤスリで表面を整えます。
そこから徐々に細かいヤスリにしていくとキレイな表面に仕上がります。
木工に限らず、研磨の作業と言うのは基本的には粗い目のものから徐々に細かい目のもので研磨していきます。
研磨の単位
砥石や研磨布紙(やすり)などのパッケージを見ると「#120」や「120」といった数字が書いています。
この数字は目の粗さ(または細かさ)を数字で表したもので、「粒度(りゅうど)」と呼ばれます。
粒度は数字が小さくなるほど粗くなっていき、大きくなるほど細かくなっていきます。
つまり、小さな数字のものから研磨していき、段々と数字の大きなもので研磨して仕上げるということになります。
また、知っておきたい事として、粒度120と400では数字上の差は280しかないのですが、研磨した時の感覚ではかなりの違いがあります。逆に粒度3000と5000では数字上は2000の差がありますが、研磨した時の感覚はあまり差が感じられません。
この違いを知っておかないと、粗いものから細かいものへ移る時にどれくらいの粒度の幅で研磨すれば良いのか判断するのが難しくなります。
湿式研磨と乾式研磨
砥石を使った研磨では作業の中で水や研削液を使用することがあります。
水や研削液を使用する作業のことを「湿式」といいます。
反対に水や研削液を使用せずに直接研磨する作業を「乾式」といいます。
湿式の場合は粉塵や熱が出ないなどのメリットがありますが、現場を濡らしてしまうということがあるので、どちらがいいというよりも現場の環境や状況に合わせることが多いようです。
Copyright © 2015 NANIWA ABRASIVE MFG.CO.,LTD. All Rights Reserved.